名前よりも、こころに残った音──“AOR”という言葉のまえに。
≋ Gentle Waves no.8 ≋
それが、わたしの“Gentle Waves”のはじまり。
【1】AORとの出会い
【2】日本と海外――言葉のずれ、感覚のちがい
【3】わたしの中のAOR、そして“Gentle Waves”
【4】名前よりも、残るもの。
【1】AORとの出会い
名前を知る前に、
わたしはその音に、恋をしていたのかもしれない。
まだ名前を知らないころ。
「なんだか、ちょっと泣きそうになる」
「やさしくて、すこし都会的で、夜っぽい」
……そんな曲たちが、子どものころからなんとなく好きだった。
聴くと、不思議とこころになじんで、前から知っているような、
聴くたびに好きになっていくような――
そんな感覚はいまも覚えているし、いまも変わらない。
何度聴いても、胸がきゅっと締めつけられる。
きっとわたしは、出会ったときから、
この音たちにずっと恋し続けているんだろうな、と思う。
誰かが“これ、好きかも”って思った、その瞬間に生まれる名前なのかもしれないね。
でも、あとから知った。
あの音たちは、どうやら“AOR”という名前で呼ばれているらしいこと。
「アダルト・オリエンテッド・ロック……?」
10代のわたしには、ちょっと大人すぎて、びっくりしてしまった。
けれど、いま思えば――
そのちょっとよくわからない、名づけと中身の“ずれ”も、
AORという音楽の、静かな自由さを物語っている気がする。
でもね、名前を知らなくても、わたし、ずっと前から恋してたんだ。
【2】日本と海外──言葉のズレ、感覚のちがい
AORという名前を知ってから、あらためて調べてみた。
すると、少しずつ違う景色が見えてきた。
日本では1980年代を中心に、
“西海岸っぽさ”や“都会の憂い”、“夜のドライブ”といった、
感覚的なイメージとともに定着していったAOR。
一方、海外では “Album Oriented Rock”。
シングルではなく、アルバムを通して聴かれるロックのこと。
ラジオで流れる、Fleetwood Mac や Journey、Foreigner、Boston……
少し重めで、力強いサウンドもそこに含まれていた。
定義は、国や時代によって、ゆっくり変わっていく。
やがて、日本では日本独自の“耳”が育っていって、
AORという名前も、少しずつ別の響きを持ちはじめたように思う。
「AORが好き」って言っても、
きっと、みんな少しずつちがう音を思い浮かべている。
その“ゆらぎ”が、AORらしさなのかもしれない。
【3】私の中のAOR、そして“Gentle Waves”
前の章でもふれたように、
AORといえば、一般には「洗練された」「都会的」「メロウ」
といった言葉で語られることが多い。
でも、わたしにとってのAORは、もう少し広くて――
ただひとつ、「こころに触れて、そっと残るかどうか」。
そんなふうに感じる音たちは、
ジャンルや時代を越えて、どこかでつながっている気がした。
そう考えたとき、ふと立ち上がってきたことばがあった。
「Gentle Waves」
やさしくて、
軽やかで、
でもなぜか、胸に静かに残っていく。
“心地よいのに、少しせつない”
“聴くたびに、遠い記憶がよみがえる”
AORにも、
わたしの中のGentle Wavesにも、
そんな“音の波”が、たしかにゆれている。
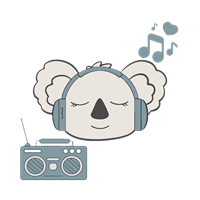
【4】名前よりも、残るもの。
たとえジャンルの名前がついていなくても、
誰かのこころに、“波のように残る音”があるなら――
それだけで、きっと十分なんだと思う。
名づけよりも、大切なことがある。
その音が、また誰かの夜に、そっとふれるなら。
こころにふいに残る、“あのとき”のことなんだと思う。


